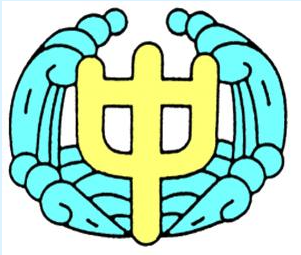雷!!!(2)かみなりの発光がなぜ稲妻と呼ばれるの?
古代、稲が実る時期である秋に雷が頻繁に発生しており、雷が多い年は豊作になると経験的に知られていた。人々は、この雷が稲にとって不可欠な存在であると考え、稲を「稲」に、雷を「夫」に例えた。その後、稲の「妻」として稲妻(いなづま)という言葉が生まれ、その放電現象である光を「稲妻」と呼ぶようになった。https://kotobaken.jp/qa/yokuaru/qa-121/

雷のなぜ!!!(1)で触れたように、雷の放電によって発生する高エネルギーが、空気中の窒素分子(N₂)と酸素分子(O₂)が結びつけさせ、窒素酸化物(NOx)を生成します。生成された窒素酸化物は、さらに酸素によって酸化され、硝酸(HNO₃)などへと変わります。この硝酸が雨水に溶け、地上に降り注ぎ、土壌の肥料となり、植物の根から吸収されて栄養源となります。
https://www.umk.co.jp/otenki-blog/post-159.html

世界中の雷による年間の窒素固定量は5TgN/yと試算されており、海域と陸域での微生物(根粒菌やアゾトバクター菌等)による窒素固定量の1/40ではあるが、稲妻の窒素固定効果が大切な肥料としての窒素元になる事が裏付けられている。
https://www.asahigroup-foundation.com/support/pdf/report/2019/13.pdf
窒素は蛋白質の重要な構成元素で、植物にも動物にも欠かせない元素です。一般に硫酸アンモニウムや硝酸塩として植物の根から吸収される。葉には葉緑素として約4%の窒素が含まれ、牛や馬が草を食べて肉の元になっている。根粒菌と共生する豆類は多いもので16%も蛋白質が含まれており、菜食主義者の大切な蛋白源である。尚、お米にも7%、小麦の薄力粉に7%、強力粉には13%の蛋白質が含まれる。窒素を人工的に合成出来る前は、根粒菌や海藻や雷で固定された窒素を植物が根から吸収して葉に貯えられ、これが枯れて堆肥として、あるいは動物の糞尿として窒素は循環していた。1900年前半にハーバーボッシュ法が発明され、アンモニアが工業滴に合成され、窒素肥料として世界の食料増産に貢献した。