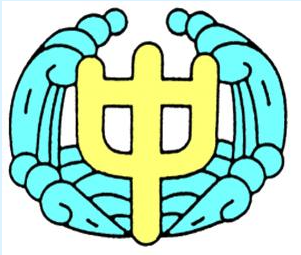雷(5):雷に関するよもやま話!
雷に関して、気になっていたことに関して、AIに聞いてみました。
◎電気を通しやすい物=危険というと聞いていますが本当ですか?
電気を通さないもの=安全とは限りません。落雷に対する十分なデータがなく、また、実験等による検証が行えなかった時代には、金属製品を身につけていると落雷に遭いやすいという誤った認識が一般化されていました。これは、落雷で死亡した人が身に着けていた金属や衣類の金属が溶けていたり、金属に触れている部分の皮膚が著しい熱傷(やけど)を負っていたことから生じた誤解です。現在では、身につけた金属製品には、人体を流れる電流値を減らす一定の効果(=ジッパー効果)があることが、事故の実例や実験により確かめられています。ただし、傘やゴルフクラブなどを頭より上に掲げることは、雷を誘引するため論外です。
同じく、身につけた長靴やレインコートなどのゴム製品に安全効果があるというのも誤った認識であることが立証されています。雷の高電圧に対し、ゴム製品の絶縁効果は皆無であることが確認されています。
◎飛行機に雷が落ちても安全ですか?
機体の損傷や電子回路に事故が起こると墜落に繋がるので,何重もの対策がなされています。
・飛行中の落雷対策: 気象レーダーで雷雲を避ける:飛行機の機首にある気象レーダーが、電波の反射を利用して雷雲の位置や強さを把握します。パイロットは、赤・黄・緑で表示される危険度を見て、雷雲を避けるルートを選択します。
・放電装置: 翼の先端や後端に設置された針のような「放電索(スタティック・ディスチャージャー)」が、万が一被雷した際の雷の電気を空中に放出する役割を果たします。
・静電気対策: 放電索は、飛行中の空気との摩擦で機体に溜まる静電気を放出する役割も担っています。静電気が帯電すると雷に撃たれやすくなるため、この装置は被雷の確率を減らすことにもつながります。
●落雷しても安全な理由:
・飛行機全体が金属製で「ケージ効果」が働く:飛行機が金属で覆われた乗り物であるため、雷が機体の表面を伝って大地に流れる(ファラデーのケージ効果)ことで、機体内部への被害を防ぎます。
・機体が電気を通しにくい構造:燃料タンクの周りの二重構造化や、金属製のパイプに配線を通すことで、雷電流の誘起電圧によるスパークや火災を防ぐ工夫がなされています。
このように、飛行機は複数の対策を組み合わせることで、落雷時も安全に飛行できる体制が整えられています。
◎避雷針のはなし - (出展;関東機電株式会社)
避雷針(ひらいしん)は、雷の電気を建物に安全に誘導し、地面に逃がすことで、建物本体や人命を直撃雷から守るための装置です。屋上に針のような金属製の受電部を設置し、そこから導線を通り、地面に埋められた金属製の電極(接地極)に雷電流を安全に放電します。避雷針は建物の保護範囲を限定しており、内部の電子機器を誘導雷から守るには、避雷器(SPD)の併用が推奨されます。
●避雷針の仕組み
・雷の誘導:避雷針は、雷が落ちやすい高い場所に設置され、雷の「お迎え放電」を誘導して自らに引き込みます。
・電流の導通:避雷針に落雷した雷の電気は、針から導線(引き下げ導線)を通って流れます。
・安全な放電:導線は地面に埋められた金属製の接地極につながっており、雷電流は大地に安全に流れて放電されます。
●避雷針の機能と限界
・建物の保護:直撃雷から建物の破損や火災、人身事故を防ぐことを目的としています。
・保護範囲:避雷針の保護範囲は、建物の下から左右約60度(保護角)と限定されており、その範囲外では保護効果は期待できません。
・誘導雷への対応:避雷針は建物の本体を直撃雷から保護しますが、雷の「誘導雷」による電子機器への被害は防ぐことができません。この誘導雷サージから電気機器を守るためには、別途「避雷器(SPD)」の設置が必要です。
●関連する対策
・避雷器(SPD):落雷時に過度な電圧や電流が電源線や通信線から建物内に流れ込むのを防ぎ、パソコンや家電などの電子機器を守ります。
・落雷抑制避雷針:近年では、電荷を抑制することで落雷自体を発生させない、または低減させる「電荷中和型避雷針」や「落雷抑制避雷針」も登場しています。
◎その他_雷のよもやま話
●神話と伝説
🔵日本の雷神(らいじん): 日本神話に登場する雷の神様です。太鼓を打ち鳴らして雷を起こす姿で描かれ、恐れられると同時に信仰の対象でもありました。
・稲妻(いなずま): 昔の日本では、雷の光(稲妻)が稲を実らせると信じられていました。稲妻の語源は「稲の夫(つま)」で、稲の豊作をもたらす存在と考えられていたのです。
・おへそを隠す: 雷が鳴り始めると、「雷様におへそを取られる」という言い伝えがあります。これは、子供が冷えで腹痛にならないよう、お腹を冷やさないようにという昔の人の知恵が由来とされています。
・雷獣(らいじゅう): 落雷とともに出現するとされた伝説上の妖怪です。江戸時代の文献にも記録があり、現代のアニメキャラクターのモチーフになったという説もあります。
🔵世界の雷神: 世界各地にも雷を司る神が登場します。
・ギリシャ神話のゼウス: 全能の神であり、雷を武器として使います。
・北欧神話のトール: 雷鳴はトールが乗る戦車の音、稲妻は彼のハンマーが放つ光だと信じられていました。
・北米のサンダーバード: 多くのネイティブアメリカンの部族に伝わる神話上の鳥で、雷の精霊とされています。
◎豆知識とことわざ:
・「くわばら、くわばら」: 落雷を避けるためのおまじないです。平安時代に、菅原道真の領地であった京都の「桑原」にだけ雷が落ちなかったという伝説が由来とされています。
・「遠くの雷より近くの雨」: 遠くで鳴っている雷よりも、近くで降っている雨の方が身近な危険だという意味です。
・「雷のあとにはタケノコが出る」: 雷の後に雨が降ってタケノコがよく育つ、という経験則から生まれたことわざです。
関連して、雷でテレビや家電が壊れた場合,火災保険が効きますので、
諦めないで下さい。。
https://kyoyomo.com/safety-education005/1484
以上
雷について5回に亘り掲載しました。少しでもお役に立てれば幸いです。