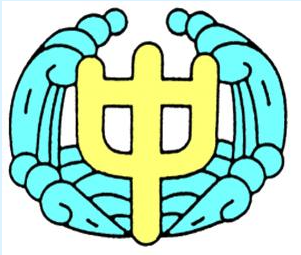雷!!!(1):発生から落雷のなぜ
8月25日に稲妻を撮影し、雷が二往復している写真を本欄に掲載しました。今回は、雷の謎について、纏めて見ました。
①:なぜ雷雲に電気が発生するの?
⇨夏の積乱雲*は、地面が太陽熱で熱せられ上昇気流が起こり、時として1万m迄も登る。1万m上空の気温は地表よりも60℃低いので、上昇気流中に含まれる水蒸気は氷滴となり、ぶつかり合う。氷がぶつかって割れたり擦れて剥がれると氷の粒子間の電子に偏りが生じ、この電子が雲の中に溜まる。
(*雷雲の種類:真夏の熱雷、季節の変わり目の界雷、台風等の渦雷、噴火による火山雷)

https://kids.gakken.co.jp/kagaku/kagaku110/science0314/
②:雷はなぜ落ちるの?
この偏った電子が一定量を超えると(大きな雷雲になるとその電圧は1億V以上になる)、空気と言う絶縁体**の壁を突き破って、放電が始まる(絶縁破壊***)。
(**:雷雲中では液体の水では無いので電気は流れ難い。
***絶縁破壊:絶縁体に電圧を印加すると、電界が発生し、微小な漏れ電流が流れる。電圧が一定の限度(絶縁破壊電圧)を超えると、絶縁体内に自由な電荷担体が急増する。電荷担体の増加に伴い、電気抵抗が急激に低下し、絶縁性が失われた絶縁体は導電体となり、大電流が流れて破壊される現象。)
③:稲妻はなぜギザギザになるの?
稲妻の発生過程は以下のように考えられている。
・雷雲の底部からマイナス電荷(ステップトリーダー)が大地に向かって走る。
・地表の避雷器や背の高い木から上向きにステップトリーダーのお迎え放電(ストリーマー)が発生。
・ステップトリーダーとお迎え放電が結合することで、電路を形成して雷雲と大地が電気的に結ばれる。
・形成された放電路を通って、今度は雲から地面に向かって非常に強力な電流(リターンストローク)が流れる。これが稲妻の本体であり、雷鳴や熱、光の原因となる。
・対地放電を落雷、雲の間での放電を雲放電と呼ぶ。
・放電中は、電子やイオンが大気中の窒素や酸素にぶつかりながら電気の通りやすい道(ステップトレイル)を作るので、ぎざぎざの稲妻となる。
https://www.otowadenki.co.jp/basic4

④:落雷するとなぜゴロゴロと鳴るの?
稲妻が起こるときの電気エネルギーの約 4分の3は,イオン化した分子の衝突等によって,稲妻近くの大気の加熱に消費される。一瞬の間に温度は 3万℃程度にまで上昇し,その結果、電光に沿って大気が急激に膨張して衝撃波****が発生し,空中を伝播する。これが雷のゴロゴロとかビシッと音がする原因である。雷がよく聞こえるのは稲妻から約 15kmの距離までで,普通は 25kmで聞こえなくなる。雷放電そのものは 0.5秒以下というごく短時間の現象であるが,放電路の長さが 2~14kmにもなるので,耳までの到達時間が異なり,また干渉などによって,音はごろごろと低くなる。
(****衝撃波とは、音速を超えて伝播する急激な圧力上昇を伴う波の事。物体が音速を超える速度で移動する際に、周囲の流体(空気や水など)が急激に圧縮されることで発生し、爆発、雷、超音速飛行などで見られる膨張波。)
⑤:雷の電気はなぜ捕集出来ないの?
一回の放電のエネルギーは15億Jにもなる(単位はジュール、⇨=3.6億cal→200Lのお風呂90杯を20℃から40℃に加熱出来るエネルギー)が、下記の理由で捕集は難しい。
・雷の放電は1/2〜1/1000秒程度と短いので電流が20万A(アンペア) *****にもなり設備が大きくなる。
・落雷は瞬間的な現象でこれを待っている時間の方が長いのと、何処に落ちるか分からない。
・落雷までの間に雷の電力の3/4は空気中での反応や発熱や電磁波として使われてしまい、全エネルギーを捕集して利用する事は難しい。
(*****: 家庭の電線の許容電流が15Aから想像して下さい。)
https://www.franklinjapan.jp/raiburari/topics/others/1417
次回は、なぜ雷光は稲の妻なのか、雷雲の上空40~80kmの高度で発生する**超高層雷放電(スプライト、ブルー・ジェット、エルブスなど)の不思議、雷が来たらどうするか等について調べた結果を書きます。