食べられないカシパンを拾った?
2025年5月12-14日に房総半島でゆっくり遊んできました。

九十九里海岸では5cm級のハマグリの貝殻があちこちに散らばっており、この貝殻を蹴飛ばしている内に、幾つかの中身の入った(生きている)貝を見つけましたが、漁業権が設定されているので、「持ち帰ると犯罪」と大きく書かれていました。このサイズの焼きハマグリは2ヶで1000円もするようです。
ハマグリの貝殻に混じって下の写真に示した奇妙な貝殻?を拾いました。大きさは直径4-5cm程度、厚みは5mm程度で、中は中空(砂が充満)で、中央部分に小さな穴が空いており、いずれも藤壷が一つ付いていました。模様はヒトデに似ていますがヒトデの化石では無さそう。インターネットで調べて、漸くハスノカシパンに辿着いた。

https://uni-club.amebaownd.com/posts/6696676
ウニの一種だそうで、砂の表面に潜って砂の中の有機物を食べているそうです。生きている時は下の写真のように短い刺に覆われているとのこと。体の構造は、右の図にあるように花紋のある面の裏の平らな腹面の真ん中に口が有り、小さな刺が有機物をリレーして口に運ぶそうです。


http://www.biology.tohoku.ac.jp/lab-www/asamushi/custom32.html)http://blog.livedoor.jp/enosima_kai/archives/47968605.html
ただ、殆ど全てのハスノカシパンには一ヶの藤壷が付着していた。これは一体何なのだろう。勝手に妄想を巡らしてみた。死んだカシパンに藤壷が付いたとも考えられるが、ネットで調べると、生きているカシパンにも藤壷が付いているとの事。 藤壷はプランクトンを食べているので、大きなウニを直接捕食するとは思えない。浅い砂に潜って刺を動かして移動するハスノカシパンにとって藤壷の付着は移動の妨げになり、餌が取れずに死亡したと考えては如何でしょうか。
下の動画は北大水産 動物生態学研究室のYouTubeです。中々良く纏まっていますので、ご参考まで。
次回は、南房総を纏めます。
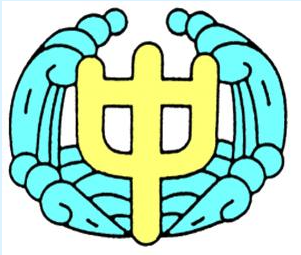
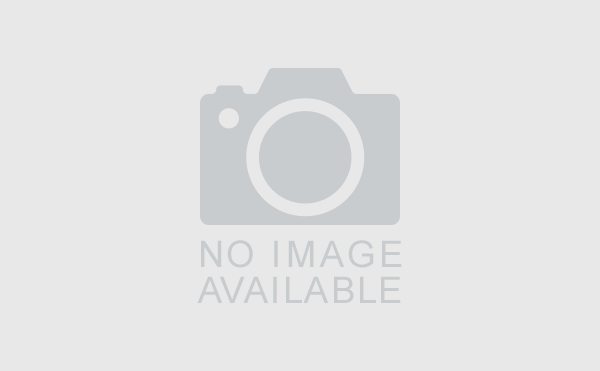
5月1日~3日、2泊3日で、函館(五稜郭・夜景・朝市)と青森(三内丸山遺跡・弘前城)を妻と長男で巡りました。妻が飛行機がダメで、新幹線・船・新幹線を利用した旅でした。桜と夜景と縄文。城としだれ桜がゆれる先に岩木山・・・新青森駅で買った「津軽」の駅弁が、何とも言えない思い出となりました。
先生・・・高砂小学校の「二宮金次郎」の像は?どこに在るのでしょうか?5月25日に、さいたま市長選の投票日で、久しぶりに訪ねました。昔あった金次郎の像が、思い出され構内をめぐりましたが、見あたりません。「勤勉実直」のかがみ金次郎さん探しましたがおりません。
「木を背負い・本を読む」姿は、私には程遠い姿です。が、あえて言えば働いて汗を流した40年以上は、負けません。これが私の誇りだ在り人生と思い日々生きております。
学無くて 汗流してや わが人生
コメントでは無く、投稿に移しました。